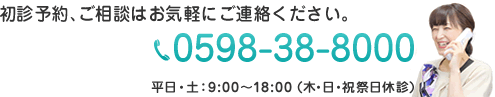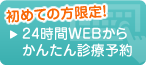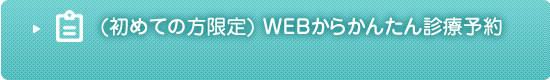せこ歯科ブログ
6/18名古屋で研修を受けてきました
今日は父の日ですね。本来なら家にいて自分たちの父親へ感謝の気持ちを伝えるべき日ですが、今日も名古屋で研修を受けてきました。
昨日は診療後、アシスタントのスタッフたちとともに顕微鏡について話、知識の差、どうやったら伝わるのか伝え方と知識について2時間話し合いました。せこ歯科のアシスタントも勉強熱心で一週間前に比べかなり成長していました。その前向きさに後押しされて今日も講習会に参加してきました。
いま、現在せこ歯科で用いているインプラントの特徴をより理解するために講習を受講してきました。様々な特徴を理解し適所適材、最適なインプラントの選択を行うための知識、そしてインプラントの植立する位置、方向の追求を図るため学び、練習を行いました。受講生は6名と少数だったのと昨日のアシスタントの前向きさに後押しされて事前に考えておいた質問事項、そして受講中に気になったことすべて聞くことができました。
お隣に座った25歳ほど年の離れた先生とは自分一人で診療しているとついつい自己流に走ってしまう。こういう場に出てくることによって自分を見直すことができるよね。という話もし、学べることの幸せを感じました。
この研修をせこ歯科で活かせるように日々励んでいきます。
せこ歯科クリニック 副院長 渡部 浩司
6/4東京でセミナーに参加してきました。
6/4東京で研修を受けてきました。
今回もインプラントの研修だったのですが今回は摂食嚥下についても学びました。
五月より往診にも携わらせていただくことも多くなり、摂食嚥下について耳にする機会は確実に増えてきました。そんななかこのインプラントのセミナーでも耳にすることとなりそろそろ勉強する時期と感じています。
インプラントの大きな目的は摂食すること、ただ、咬めるだけではなく口腔内周囲の筋肉、嚥下に携わる筋肉についても学びインプラントの理想的な位置等も学びました。
発生では魚や、鳥にはなく、哺乳類にあるものそれは頬であるという話から、その哺乳類のなかでも人間は唇が発達しているという話を聞き、嚥下(飲み込み)の最初は口であることを改めて自覚し、ただ、筋肉があるだけでは口からこぼれてしまうので唾液があり、唇の赤いところは角化が少なく、血液の色が透けて見えるためであること。角化していると口が閉じれず、飲み込みずらいという話を聞きました。
飲み込むのに必要な筋肉を改めて勉強しなおし、高齢社会に突入するうえでの基本知識ついても学びました。
全身の中の1口腔を扱える歯科医師を目指して日々研鑽していきます。
せこ歯科クリニック
渡部 浩司
4/15~16で東京で研修を受けています。
4/15お休みをいただき研修会に参加しています。
今回も前回に引き続きインプラントの内容です。
今回はインプラントを入れた直後に噛ませるために必要な条件について学んでいます。入れた直後から噛ませるにはインプラントの種類、骨の質、インプラントを入れる技術、この三つの要件を満たしたときでしか直後に噛ませることはできないのですが、そのうちのインプラントの種類、入れる技術について学んでいます。種々のインプラントの特徴があり、直後に噛ませるには適したインプラントの選択が必要となります。また技術的にはぶれないインプラントを入れるための穴を形成することやはり位置、方向性の重要性について学び、実習を受けています。実習では実際の術式で行い、ISQという振動によってインプラントの初期の安定性を図る機械で測定しすすめました。実際、9本のインプラントを植立しそれぞれに3回ずつ測定を行いました。どの状態が一番ベストなのか?どのようにインプラントを植立させるための穴を形成するのかについてつかめた感じがします。
そして、インプラントの定期検診で見るべきポイントとその状況の応じた対策。インプラントは所詮異物でしかないこと。歯茎から出ている釘だと思い丁寧に管理することの重要性について学びました。
いろいろな先生の発表もあり、やりたい治療をするのではなく、患者さんの立場に立った治療を行うこと。先を見越した治療を行っていくことの必要性、そして何よりインプラントを守るための治療ではなく、患者さん自身の歯を守るためにインプラントという道具を使うことについて再度確認しました。
この、学びをせこ歯科にも活かしていきます。
せこ歯科クリニック 副院長 渡部 浩司
矯正のセミナーに参加してきました
3月19日、東京で矯正のセミナーに参加してきました。
私が参加しているこの矯正セミナーは回数が決まっているわけではなく、何回でも参加することができ、皆で症例について学んでいく場です。
今回も講義と症例検討会がありました。今年の講義のテーマは矯正のゴールを迎えるにあたってというものです。虫歯などと違い、矯正のゴールに関しては医療者が勝手に決めるものではありません。一定の目安はあるものの、患者様や保護者の方の希望も大きく関係してきます。
この目安とはどのようなものでしょうか?次にあげていきます。
①安定したかみ合わせの確立
②スムーズな顎の運動の達成
③鼻呼吸の確立
④歯が生えている骨の形が整っている
⑤舌や唇の癖が改善した
まだまだありますが、ざっと上げるとこのようなものがあります。矯正というと歯並びがキレイになるというイメージが一般的がと思いますが、それに加えて治療のゴールにはお口の機能の回復といったことが大切になってきます。
前々からお話させていただいているように、歯並びに悪影響を与える行動は多々あります。例えば頬杖をつく、片方の肩にしかバッグをかけない、うつぶせ寝や横向き寝などあげればきりがありません。共通しているのは偏った体の使い方です。
これらの行動が歯並びを悪くする可能性があるので、矯正装置による治療が終わった後も、バランスの良い体の使い方をしないと、後戻りが起こってしまいます。これだけ日常のふとした行動が歯並びに関係しているとすると、装置を外した後も体の使い方に気を付けていただく必要があります。
装置を使ってのゴールを迎えた後も、ご自身で歯並びを守っていくために偏った体の使い方をやめ、自分にそのような癖がないか考えていただく必要があります。そういった意味では装置を使わない治療はずっと続くと考えられます。難しいことではありません。ご自身の行動を振り返っていただき、なにか癖があれば改善してもらうことで健康な体作りをすることができると思います。
せこ歯科クリニック 田岡 則子