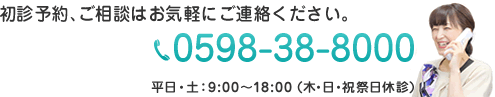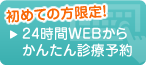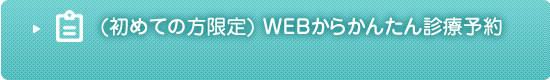せこ歯科ブログ
名古屋でセミナーを受けてきました
12月11日(日曜)名古屋にある開業医さんで、セミナーを受けてきました。
今回は、歯や歯の神経を残すにはどのような診療方法がいいのかについて講義と実習を受けてきました。虫歯になってしまった歯でお痛みがある場合、神経をとっていくのが一般的ですが、歯に直接薬をおくことで神経を残せる可能性があります。その手技についても実習で学んでまいりました。
また、折れてしまった歯、虫歯で大きくかけてしまった歯をどうすれば抜歯することなく、再び歯として機能させることができるのかについても学んできました。さらに抜歯が適応と思われる症例でも残していけるような治療方法についても説明を受けてきました。
実習では、痛くなくよく効かせることができる麻酔の打ち方をお互いに打ち合うことで練習したり、歯の神経を残すような手技を身につけてきました。
今回のセミナーの内容をドクター同士で話し合い、今後の治療にどうしたら生かしていけるかについても話し合いました。この濃いセミナー内容を診療に活かして、よりよい治療をていきょうしていきます。
ドクター一同
11月13日名古屋でセミナーを受講してきました。
皆さん、こんにちは。10月に引き続き、名古屋でかみ合わせのセミナー(5回中4回目)を受講して来ました。
全身→下顎の位置→歯並び→個々の歯の病気という順に考えるTop Down Treatment
全身←下顎の位置←歯並び←個々の歯の病気という順に考えるBottom Up treatment
双方向から考える重要性と実際の下顎の動き、顎の関節の動きに対してここの歯の動きを勉強しました。そして、僕たちが患者さんに提供している被せものを作る行程がどれだけ実際の顎の動かし方とリンクしているのかを知ることを感じました。実はごく一部でしか下顎の複雑な動きを再現していないことを理解し、それを補うためにお口のなかでの最終調整を行っているのを再度理解しました。
そしてナラティブ ベイスド メディスン(患者さんの訴えに基づいた医療)とエビデンス ベイスド メディスン(科学的根拠に基づいた医療)を両立させれる医療を提供できるように全身との関係についてより深く学べるいい機会になりました。
より質の高い医療を目指して日々研鑽していきます。
せこ歯科クリニック 渡部 浩司
10/29.30と東京でセミナーを受講してきました。
10/29.30と土曜日お休みをいただき東京で研修を受けてきました。
今回はインプラントに特化した研修でした。インプラントに対していかに患者さんの負担を減らせるのか?ということを考え尽くしてきた著名な先生による研修で半年前から計画を立てての受講でした。
歯茎の切り方ひとつでも術後腫れないための考え方、人間の治癒力を利用して患者さんが満足いくインプラント治療をおこなう考え方、そして数多くの実習に基づく手技、自分の普段行っている手技でどれくらい力をかけてインプラントを埋めているのかを知るいい機会になりました。また、他社のメーカーのインプラントを用いることにより自院で使っているインプラントの特徴、利点、注意すべき点を振り返るいい機会になりました。
講師の先生の言っていた
『いかに患者さんの負担を減らして患者さんの満足を追求していくか?』
これはインプラントだけに限らず全ての治療においても求めていく必要を感じました。そして、患者さんの負担を減らしつつ満足度をあげるこの道の追求には終わりがないことも感じ、日々の研鑽によって磨かれるものと感じました。
今後、『いかに患者さんの負担を減らし、患者さんの満足を減らすには何をすべきだったか?』を常に意識し、日々の診療に臨みます。
副院長 渡部 浩司
矯正勉強会アドバンスコース 第5回 in 明石
先日11月10日の講習をもって、Ⅲ級アドバンスコースが終了しました。
全5日間のコースの中で、実習も抜歯ケースと非抜歯ケースを行いつつ、その合間に講義を行うといった
工程で進行していき、気づいたら最終回を迎えていました。
多くのⅢ級治療のケースを見せて頂きながら、その中でどのように診断していき治療を行っていったのか、
矯正歯科出身でないDrに対してもすごく吸収しやすく講義して頂ける講師の先生方ありがとうございました。
どの勉強会に行っても講師の先生から直接聞かせて頂けることは、本を読んでるだけでは学べないことが
大変多いように感じます。
来年1月からはⅡ級アドバンスコース(上顎前突治療)が開始するので、復習をしてⅢ級で学んだことを完璧に
吸収して、来年のコースに向けて頑張っていきます。
福田 泰久
矯正のセミナーに行ってきました
11月13日、東京で矯正のセミナーを受けてきました。
今回は某歯科大学の矯正科教授の講義を受けてきました。この講義では特に小児の歯並びについて学んできました。小児の歯並びが悪くなる原因を今一度しっかり学んでおかないと、治療計画もしっかり立てることができません。今まで学んできたことと照らし合わせながら講義を聞いてきました。
ひと昔前、子供のお口の中には虫歯がいっぱいありました。まずその虫歯を治すことが歯科医師の使命のようなものでした。しかし現代の子供のお口にはほとんど虫歯はみられません。それは定期的に歯科医院に通いフッ素を塗ったり、家庭での歯磨きをしっかり行ってもらうようになったためだと思います。このことは大変喜ばしいことなのに、最近では歯並びを気にされるお母様が増えてきたように思います。
昔、歯並びが悪くなる原因として挙げられていたのは虫歯でした。虫歯により乳臼歯がなくなってしまい、そのことで6歳臼歯が前に倒れこんできてしまい、歯が生えるスペースが少なくなってしまい、結局歯並びがガタガタになってしまうというものでした。
それが、今まで歯並びが悪くなるとして挙げられていた虫歯が減少したのにも関わらず、歯並びが悪い子供が増えているのは、なぜなのでしょうか?
それは原因が変化してきているからです。現代の子供の食生活は軟らかいものが多く食されています。そのことで咀嚼が未熟となり上あごの発育不全・下の6歳臼歯の内側への倒れこみを招き、上あご・下あご共に小さくなり、歯の生えるスペースが少なくなってガタガタの歯並びになってしまうということです。
ですので、子供の歯並びを治していこうとするときには、装置であごの成長を促してあげることに加えて未熟な咀嚼についてもアプローチしていく必要があります。しっかりした咀嚼をするためには、足裏を床に着けて一口30回噛むようにしていく必要があります。生活習慣を見直すことで歯並びをよくすることができる可能性があるので、今一度、お子様の食事風景をよく観察し、たくさん噛むように声かけをしていっていただきたいと思います。
田岡 則子